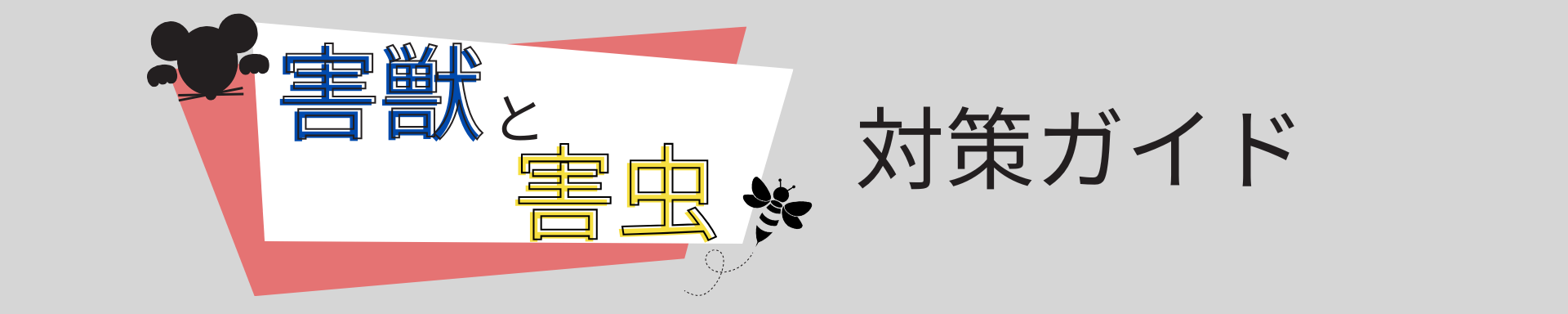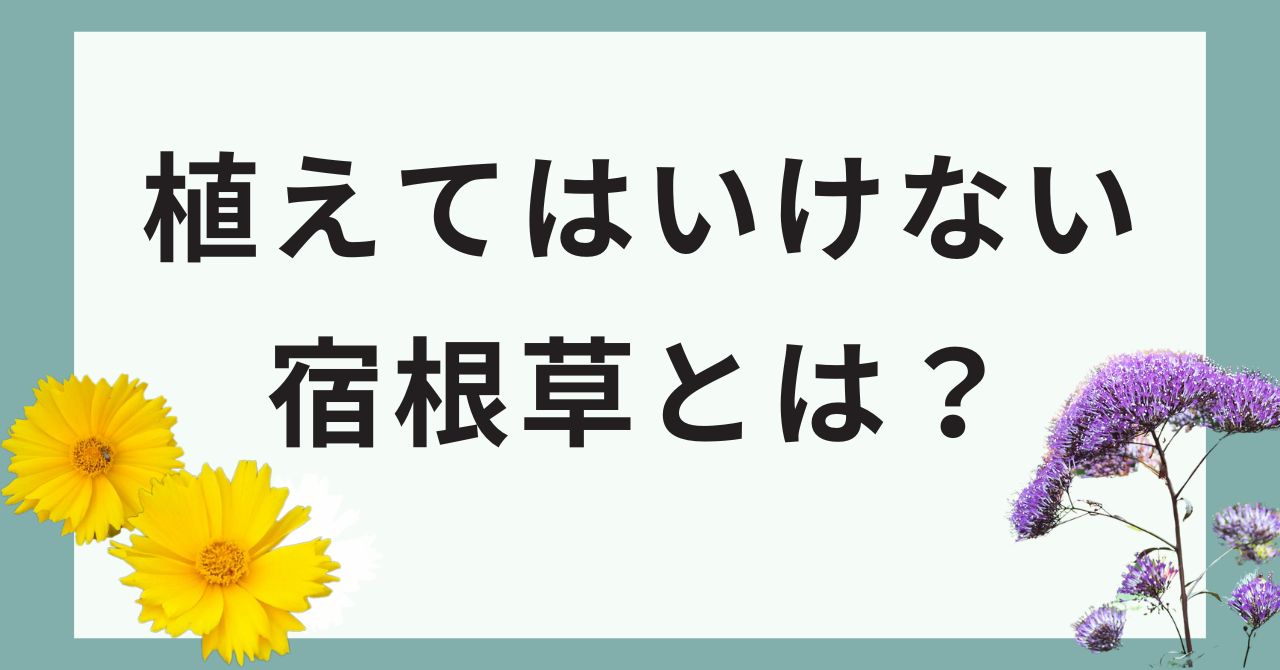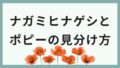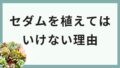ガーデニングを始めると、つい「ほったらかしで毎年咲く花」に惹かれてしまう方も多いのではないでしょうか。確かに、宿根草は一度植えると毎年楽しめる手軽さが魅力ですが、中には「植えてはいけない宿根草」も存在します。知らずに選んでしまうと、庭全体のバランスが崩れたり、手入れが想像以上に大変になることもあります。
この記事では、宿根草と多年草の違いをはじめとして、「植えてはいけない宿根草」の具体例やその理由をわかりやすく解説します。特に宿根草初心者の方にとっては、選び方を間違えると後悔につながることも少なくありません。そこで、宿根草一覧を交えながら、宿根草人気ランキングや寒冷地におすすめの宿根草なども紹介します。
また、失敗しない花壇の宿根草と低木のレイアウトや、実際に「植えて良かった宿根草」の実例まで、実用的な情報を網羅しています。美しく、そして手入れがしやすい庭をつくるために、この記事を参考にしてみてください。
- 植えてはいけない宿根草の具体的な特徴と理由
- 庭づくりにおける宿根草の選び方と注意点
- 宿根草と多年草の違い
- 寒冷地や初心者向けの宿根草の選定ポイント
植えてはいけない宿根草とは?
- 宿根草と多年草の違い
- 植えてはいけない理由とそのリスク
- 放置すると困る外来種に注意
- ほったらかしで毎年咲く花の落とし穴
宿根草と多年草の違い

宿根草と多年草は、どちらも一度植えたら何年も咲き続ける植物の分類ですが、実際には少し異なる考え方が存在します。
まず宿根草とは、冬の寒さや夏の暑さで地上部が枯れても、地下に残る根や芽が生き続け、次の年に再び芽吹く植物のことです。多年草の一種ではありますが、一般的に「冬に地上部がなくなる植物」として区別されることが多いです。
一方で多年草とは、複数年にわたって生育を続ける草本植物全体を指す広い言葉です。中には寒さに強く、一年中葉を残す「常緑多年草」も含まれます。つまり、宿根草は多年草の一部にあたり、「冬に姿を消すタイプの多年草」とも言えるのです。
この違いを理解することで、庭づくりや植栽の計画がぐっと立てやすくなります。例えば、冬も緑が欲しい場合は常緑多年草、花のサイクルを楽しみたい場合は宿根草といったように、目的に合わせた選び方が可能です。
どちらの植物も毎年花を咲かせるという点では同じですが、「地上に姿が見えなくなる時期があるかどうか」という違いを知っておくことで、庭づくりの計画ミスを防ぎやすくなります。
植えてはいけない理由とそのリスク
植物を選ぶ際に「植えてはいけない宿根草」がある理由は、手入れのしやすさや庭の環境との相性だけでなく、成長の仕方や広がり方に注意が必要なためです。特に初心者の方が知らずに選んでしまうと、後から手がつけられなくなるケースもあります。
1.繁殖力が強すぎて管理が大変
理由:地下茎や種で急速に増えるタイプの宿根草は、一度植えると想像以上に広がり、他の植物の生育スペースを奪ってしまいます。放っておくと庭全体を覆い尽くしてしまうケースもあります。
- ミント:香りが良く人気のあるハーブですが、地下茎で増殖するため放置するとコントロール不能に。
- オカトラノオ:白い花穂が美しいものの、地下茎で猛烈に広がります。


2.高さや幅が想定以上に大きくなる
理由:成長後のサイズが大きくなりすぎると、日当たりを遮ったり他の植物の生育を妨げたりします。植えた場所に対して不釣り合いになることで、花壇のレイアウトが崩れてしまうこともあります。
- ルドベキア・マキシマ:葉も花も大きく、場所をとりすぎることが多いです。
- ユウギリソウ:思った以上に背丈が伸び、風通しを悪くすることもあります。


3.病害虫を呼び込みやすい
理由:一部の宿根草は湿気や密集を好む性質から、アブラムシやカビなどの病害虫を引き寄せやすくなります。これが原因で他の植物に被害が及ぶこともあります。
- フジバカマ:湿気を好み、うどんこ病が出やすいです。
- シャクヤク:美しい花ですが、アリやアブラムシが集まりやすい傾向があります。


4.庭の雰囲気に合わない・季節感を損ねる
理由:常緑でない植物や、見た目が急に変わるタイプは、季節ごとの雰囲気を損なってしまうことがあります。特に冬場に枯れた状態が目立ちすぎると、寂しい印象を与えかねません。
- ギボウシ(ホスタ):葉は美しいですが、冬は地上部がなくなり、穴が空いたように見えます。
- アガパンサス:花期が短く、咲いていない期間は地味になりがちです。


5.土壌や気候と合わず枯れやすい
理由:寒冷地や多湿の土地に合わない宿根草を無理に植えると、育ちにくくなり、すぐに枯れてしまいます。適応しない場所では毎年の植え替えが必要になってしまうことも。
- ラベンダー:高温多湿に弱く、梅雨時期などに傷みやすいです。
- ガウラ:寒さに弱く、寒冷地では越冬が難しいことがあります。


このように、見た目や人気だけで植物を選んでしまうと、管理が大変になったり他の植物に悪影響を与えたりするリスクがあります。庭づくりを楽しむためには、性質をしっかり理解して選ぶことが大切です。
放置すると困る外来種に注意
見た目の美しさや成長の早さから人気がある外来種の宿根草ですが、放置すると予想以上に広がり、生態系や周囲の環境に悪影響を与える恐れがあります。特に日本の気候に適応しやすい外来種は、手入れを怠るとすぐに繁殖が進み、在来の植物の生育を妨げることも少なくありません。
例えば、「オオキンケイギク」や「セイヨウタンポポ」などは、繁殖力が極めて高く、雑草のようにあらゆる場所に広がります。これらは景観植物として導入された経緯があるものの、現在では一部地域で「特定外来生物」に指定され、栽培や移動が制限されているケースもあります。


このような植物を庭に植えてしまうと、除去が難しいばかりか、風や動物によって種が広がり、近隣にも迷惑をかける結果になりかねません。特に住宅街や自然が豊かな地域では、植栽の影響が周囲にまで及ぶことを意識する必要があります。
さらに、外来種の中には特定の天敵がいないために、一度根づくとほとんど抑制できないものもあります。こうしたケースでは、通常の庭仕事では手に負えず、専門業者の力を借りることになる場合もあります。
ほったらかしで毎年咲く花の落とし穴

手間をかけずに毎年きれいな花を楽しめる宿根草は、初心者にも人気があります。しかし、「ほったらかしで毎年咲く」という魅力の裏には、意外なデメリットや注意点も潜んでいます。
例えば、手入れが不要と思って油断していると、花が咲き終わった後に枯れた茎や葉がそのまま残り、庭全体が乱雑に見えてしまうことがあります。加えて、放置しているうちに花がら(咲き終わった花)が種をまき、思いがけない場所から芽が出ることも珍しくありません。
さらに、一部の宿根草は株が大きくなり過ぎて、他の植物の生育スペースを奪ってしまう場合があります。このように管理を怠ると、いつの間にか庭のバランスが崩れやすくなるのです。
また、毎年咲くからといって全く世話がいらないわけではありません。古くなった株を掘り上げて分けたり、弱った部分を取り除いたりする作業も時には必要です。
このような理由から、ほったらかしで毎年咲く花を選ぶときは、最初に管理方法や生育の特徴を調べておくことが大切です。安易に「楽そうだから」と選んでしまうと、予想外のトラブルに悩まされることもありますので、事前の情報収集を忘れないようにしましょう。
植えてはいけない宿根草に代わるおすすめは?
- 宿根草の人気ランキング
- 初心者におすすめの宿根草の選び方
- 寒冷地でおすすめの宿根草品種
- 宿根草花壇のレイアウト
- 花壇の宿根草と低木を使った配置例
- 植えて良かった宿根草の実例紹介
宿根草の人気ランキング
宿根草は毎年花を咲かせることから、多くのガーデナーにとって魅力的な植物です。その中でも特に人気のある品種には、見た目の美しさだけでなく、育てやすさや開花時期の長さといった要素が関係しています。
ここでは、家庭の庭や花壇によく選ばれている宿根草をランキング形式で紹介します。選ぶ際の参考にしてみてください。
第1位:ラベンダー

| ラベンダー | |
| 和名 | 薫衣草 |
| 草丈 | 約30〜80cm(品種によって異なる) |
| 開花時期 | 5〜7月(地域や品種によっては秋に返り咲くこともあり) |
| 花色 | 紫、青、白、ピンクなど |
| 耐寒性 | 比較的強い(イングリッシュ系は寒冷地向き) |
| 耐暑性 | やや弱い(高温多湿に弱いため風通しが重要) |
| 特徴 | 乾燥気味を好む。過湿は根腐れの原因に。 |
ラベンダーは先におすすめ出来ない宿根草として紹介しましたが、その美しさと香りの良さから人気は衰えません。
ラベンダーは夏でも気温・湿度が高くなり過ぎない北海道や東北での生育が向いています。
「高温多湿に弱く、梅雨時期などに傷みやすい」というデメリットはあるものの、「やっぱり育てたい!」という方は下記の対応をおすすめします。
1. 水はけの良い土を使用する
ラベンダーは根腐れを起こしやすいため、水はけの悪い土は避けましょう。市販の「ハーブ用培養土」や「多肉植物用土」などを使うと、水はけが良く管理しやすくなります。
2. 鉢植えで育てて移動させる
梅雨時期は風通しの良い軒下やベランダなどに鉢を移動させると、過湿を避けやすくなります。鉢植えなら日照の調整も容易です。
3. 梅雨前に軽く剪定する
蒸れを防ぐために、梅雨入り前に軽く剪定して風通しを良くします。混み合った枝葉を間引くことで、病気の予防にもつながります。
4. 株元にマルチングをしない
マルチングは保湿効果が高いため、ラベンダーには逆効果です。株元は乾きやすい状態を保ちましょう。
5. 鉢底石をしっかり入れる
鉢で育てる場合は、底にしっかり鉢底石を敷いて排水性を確保することが重要です。水が滞るとすぐに根が傷みやすくなります。
第2位:クリスマスローズ
冬から早春にかけて咲く数少ない宿根草のひとつです。シックな色合いが多く、半日陰でも育ちます。

| クリスマスローズ | |
| 和名 | 初雪起し、寒芍薬 |
| 草丈 | 約20〜50cm |
| 開花時期 | 12月〜4月(品種により異なる) |
| 花色 | 白、ピンク、紫、緑、黒、複色など品種が豊富 |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも地植え可能) |
| 耐暑性 | やや弱い(夏の直射日光や高温多湿に注意) |
| 特徴 | 落葉期の剪定や夏場の管理がやや必要 |
第3位:アジサイ(落葉低木扱いされることもあります)

| アジサイ | |
| 和名 | 紫陽花 |
| 草丈 | 約1〜2m(品種により異なる) |
| 開花時期 | 5月〜7月 |
| 花色 | 青、紫、ピンク、白など(特に青〜ピンクは土壌の酸度で変化) |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | 普通(高温多湿には比較的強いが、水切れに注意) |
| 特徴 | 剪定の時期を誤ると翌年花が咲かないことも |
梅雨の時期に大きく華やかな花を咲かせる定番の植物です。剪定や日当たり管理は必要ですが、長年楽しめる点で人気です。
第4位:ギボウシ(ホスタ)


| ギボウシ(ホスタ) | |
| 和名 | ギボウシ(擬宝珠) |
| 草丈 | 約20〜80cm(品種により小型〜大型まで幅広い) |
| 開花時期 | 6〜8月 |
| 花色 | 白、薄紫など |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも越冬可能) |
| 耐暑性 | 普通(高温多湿にはやや注意) |
| 注意点 | 冬は葉が枯れる |
冬は地上部がなくなってしまいあまり見た目が良くないというデメリットがある一方、葉の美しさが際立つ宿根草で日陰でも元気に育ちます。手入れも比較的簡単なため、初心者にも向いています。
第5位:エキナセア

| エキナセア | |
| 和名 | ムラサキバレンギク(紫馬簾菊) |
| 草丈 | 約60〜100cm(品種によって差あり) |
| 開花時期 | 6〜9月 |
| 花色 | ピンク、白、黄、オレンジ、赤、緑など多彩 |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも越冬可能) |
| 耐暑性 | 強い |
| 特徴 | 花期が長く、切り花やドライフラワーにも向く |
鮮やかなピンクやオレンジの花を咲かせ、夏から秋まで長く楽しめます。丈夫で病害虫にも強いことが評価されています。
第6位:カンパニュラ

| カンパニュラ | |
| 和名 | フウリンソウ(風鈴草)など(品種による) |
| 草丈 | 20cm〜100cm以上(品種により大きく異なる) |
| 開花時期 | 5月〜7月(春〜初夏が中心) |
| 花色 | 青、紫、白、ピンクなど |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも育てやすい) |
| 耐暑性 | やや弱い(高温多湿は苦手) |
| 特徴 | 比較的やさしく育てられるが、蒸れには注意 |
カンパニュラは品種によって性質が異なり、「風鈴のような花姿」や「星型の花」などバリエーション豊富です。特に「チャイナブルー」や「ベルフラワー」などが人気で、庭にやさしい雰囲気を演出したい方におすすめです。蒸れを防ぐために、梅雨時期は風通しの良い場所に置くと元気に育ちます。
第7位:ルドベキア

| ルドベキア | |
| 和名 | アラゲハンゴンソウ(荒毛反魂草) |
| 草丈 | 約30〜100cm(品種により差あり) |
| 開花時期 | 6〜10月 |
| 花色 | 黄色、オレンジ、赤茶、複色など |
| 耐寒性 | 普通(宿根タイプは寒冷地では冬越し注意) |
| 耐暑性 | 強い |
| 管理のしやすさ | 高い(病害虫に強く、手間がかからない) |
黄色やオレンジの明るい花が夏から秋にかけて長く楽しめます。病害虫にも比較的強く、管理が楽な点も評価されています。
第8位:サルビア・ネモローサ

| サルビア・ネモローサ | |
| 草丈 | 約30〜60cm(品種によって異なる) |
| 開花時期 | 5月〜7月(条件が良ければ秋にも返り咲きする) |
| 花色 | 青紫、ピンク、白など |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも越冬可能) |
| 耐暑性 | やや強い(蒸れに注意) |
| 特徴 | 直立する花穂に小花が密集して咲く。 花もちが良く、香りもある |
サルビア・ネモローサは、宿根サルビアの代表格とも言える存在で、整った草姿と爽やかな花色が魅力です。咲き終わった花穂を切り戻すことで、再び花を咲かせやすくなります。長期間花を楽しめるうえに、害虫にも比較的強く、ローメンテナンスな植物としてガーデナーに支持されています。
第9位:デルフィニウム

| デルフィニウム | |
| 和名 | オオヒエンソウ(大飛燕草) |
| 草丈 | 約50cm~200cm(高性種は特に背が高い) |
| 開花時期 | 5月〜7月(地域や品種により春〜初夏) |
| 花色 | 青、紫、白、ピンクなど |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも育てやすい) |
| 耐暑性 | 弱い(夏の高温多湿に注意) |
| 管理のしやすさ | やや難しい(特に夏越しに注意が必要) |
背が高く、花壇の後方に植えると迫力のある景観が作れます。ブルー系の花色が人気ですが、やや栽培にはコツが必要です。
第10位:シャクヤク(芍薬)

| シャクヤク | |
| 草丈 | 約60~100cm |
| 開花時期 | 5月〜6月 |
| 花色 | 白、ピンク、赤、紫、黄など |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地にも適応) |
| 耐暑性 | 普通(夏は風通しと水はけを良くする) |
| 管理のしやすさ | 中程度(植え替えの時期・深さに注意) |
シャクヤクは、見事な花姿と香りの良さで古くから親しまれてきた宿根草です。ボタンよりも茎がしっかりしていて倒れにくく、初心者でも育てやすいのが特徴。ただし、植え付け時の深さを誤ると花が咲きにくくなるため注意が必要です。肥沃な土壌と日当たりの良い場所で、長年にわたって美しい花を咲かせてくれます。
虫が付きやすいというデメリットに対しては下記の対応もおすすめです。
・コンパニオンプランツを活用する
例えば、アブラムシが嫌うマリーゴールドやハーブ類(ミントやバジル)を近くに植えることで、虫を寄せ付けにくくする効果が期待できます。
・こまめな観察と物理的除去
毎日チェックする習慣をつけて、虫を見つけたら早めに取り除くことが効果的です。アブラムシならガムテープなどでペタペタと取るのも一つの方法です。
・水で洗い流す
アブラムシ程度なら、水で吹き飛ばすだけでもかなり軽減されます。スプレーボトルでしっかり噴射してみましょう。
このように、宿根草はそれぞれに異なる魅力があります。選ぶ際は「日当たりの条件」「育てる手間」「開花時期」などをチェックし、庭のスタイルや管理のしやすさに合うものを選ぶのがおすすめです。
初心者におすすめの宿根草の選び方
宿根草は毎年花を咲かせるため、長く楽しめるのが魅力です。ただし、品種によって育てやすさに差があるため、初心者は慎重に選ぶ必要があります。ここでは、ガーデニング初心者に向けた宿根草選びのポイントを詳しく解説します。
育てやすさ
まず注目したいのは「育てやすさ」です。病害虫に強く、極端な手入れを必要としない品種であれば、忙しい方でも無理なく続けられます。例えば、ヒューケラは暑さ寒さに強く、葉色も豊富なため、初心者でも管理しやすく人気です。

| ヒューケラ | |
| 和名 | ツボサンゴ |
| 草丈 | 約20〜40cm(花茎含めると最大60cmほど) |
| 開花時期 | 5〜7月(品種により異なる) |
| 花色 | ピンク、赤、白、紫など |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも越冬可能) |
| 耐暑性 | 普通〜やや弱い(夏は風通しと半日陰が理想) |
| 特徴 | 初心者でも育てやすく、手間がかかりにくい |
環境への適応性
次に重要なのが「環境への適応性」です。日当たりの良い場所で育てたいのか、半日陰の花壇を彩りたいのかによって、選ぶべき植物が変わります。日陰が多い庭にはギボウシ(ホスタ)が適しており、日差しの強い場所にはエキナセアやルドベキアが向いています。

| ギボウシ(ホスタ) | |
| 和名 | ギボウシ(擬宝珠) |
| 草丈 | 約20〜80cm(品種により小型〜大型まで幅広い) |
| 開花時期 | 6〜8月 |
| 花色 | 白、薄紫など |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも越冬可能) |
| 耐暑性 | 普通(高温多湿にはやや注意) |
| 注意点 | 冬は葉が枯れる |

| エキナセア | |
| 和名 | ムラサキバレンギク(紫馬簾菊) |
| 草丈 | 約60〜100cm(品種によって差あり) |
| 開花時期 | 6〜9月 |
| 花色 | ピンク、白、黄、オレンジ、赤、緑など多彩 |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも越冬可能) |
| 耐暑性 | 強い |
| 特徴 | 花期が長く、切り花やドライフラワーにも向く |

| ルドベキア | |
| 和名 | アラゲハンゴンソウ(荒毛反魂草) |
| 草丈 | 約30〜100cm(品種により差あり) |
| 開花時期 | 6〜10月 |
| 花色 | 黄色、オレンジ、赤茶、複色など |
| 耐寒性 | 普通(宿根タイプは寒冷地では冬越し注意) |
| 耐暑性 | 強い |
| 管理のしやすさ | 高い(病害虫に強く、手間がかからない) |
サイズ感
さらに「植える場所のサイズ感」も考えてみましょう。例えば広い花壇に背丈の高い宿根草を植えると見映えしますが、狭いスペースに広がりやすい植物を入れると管理が難しくなります。シバザクラやリシマキアのようなコンパクトな品種は、限られたスペースでも扱いやすく便利です。

| シバザクラ | |
| 草丈 | 約10〜15cm |
| 開花時期 | 4〜5月 |
| 花色 | ピンク、白、紫、青、複色など |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも冬越し可能) |
| 耐暑性 | 普通(高温多湿にやや弱い) |
| 管理のしやすさ | 比較的高い(蒸れやすいので剪定が必要) |

| リシマキア | |
| 別名 | ミズホオズキ、ヌマトラノオ など品種により異なる |
| 草丈 | 約20〜60cm(品種により差がある) |
| 開花時期 | 5〜8月 |
| 花色 | 黄色が主流(一部にピンクや白もあり) |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | 普通 |
| 管理のしやすさ | 高め(繁殖力が強いので増えすぎに注意) |
開花時期をずらす工夫も
最後に、「開花時期をずらす」工夫をすることで、一年を通して庭を華やかに保つことができます。春に咲くデルフィニウム、夏のガウラ、秋に強いアスターなど、時期をずらした組み合わせがおすすめです。

| デルフィニウム | |
| 和名 | オオヒエンソウ(大飛燕草) |
| 草丈 | 約50〜200cm(高性品種が多い) |
| 開花時期 | 5〜7月(品種によっては秋にも開花) |
| 花色 | 青、紫、白、ピンクなど |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | やや弱い(高温多湿に注意) |
| 管理のしやすさ | 中程度(支柱が必要な場合あり) |

| ガウラ | |
| 和名 | ヤマモモソウ(山桃草) |
| 草丈 | 約60〜120cm |
| 開花時期 | 5〜10月と長期間開花 |
| 花色 | 白、ピンク、薄紅色など |
| 耐寒性 | やや強い(一部品種は寒冷地で防寒が必要) |
| 耐暑性 | 強い |

| アスター | |
| 和名 | エゾギク |
| 草丈 | 約20〜100cm(品種による) |
| 開花時期 | 7〜11月 |
| 花色 | 紫、ピンク、白、青、赤など |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも育てやすい) |
| 耐暑性 | 普通(高温多湿にやや弱い品種もあり) |
| 特徴 | 菊に似た花姿で、晩夏から秋に彩りを添える |
このように、初心者が宿根草を選ぶ際は「手入れのしやすさ」「育つ環境」「見た目や開花時期のバランス」を意識することが成功のカギになります。初めての一株は、暮らしのペースに合ったものを選ぶことから始めてみてください。
寒冷地でおすすめの宿根草品種
寒冷地でガーデニングを楽しむには、冬の厳しい気候にも耐えられる強健な宿根草を選ぶことが大切です。ここでは、寒さに強く、春から夏にかけて美しく咲く宿根草の中から、特におすすめの品種を紹介します。

| アキレア | |
| 草丈 | 30〜100cm(品種によって異なる) |
| 開花時期 | 初夏〜秋(5月〜9月頃) |
| 花色 | 白、黄色、ピンク、赤、オレンジなど多彩 |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも越冬可) |
| 耐暑性 | 普通(高温多湿が続くと蒸れに注意) |
| 管理のポイント | ・過湿を避け、株が蒸れないように間引く ・多年草だが株分けで更新が必要 |
アキレアは耐寒性が非常に高く、雪の下でも翌春には元気に芽吹きます。細かい切れ込みの入った葉と、傘のように広がる花房が特徴です。白、黄色、ピンクなど色のバリエーションも豊富で、寒冷地の花壇を彩ってくれます。

| ルピナス | |
| 和名 | ノボリフジ(昇り藤) |
| 草丈 | 50〜150cm(品種により変化あり) |
| 開花時期 | 春〜初夏(4月〜6月頃) |
| 花色 | 紫、ピンク、白、黄、赤、青などカラフル |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも育てやすい) |
| 耐暑性 | 弱い(夏の高温多湿に注意) |
| 管理のポイント | ・夏越しが難しい地域では一年草扱いされることも ・風通しを良く保つ |
見た目に華やかなルピナスも寒冷地向けの宿根草です。マメ科ならではの花が塔のように咲き上がり、初夏のガーデンにインパクトを与えます。日当たりと風通しの良い場所を選ぶことで、しっかりとした株に育ちます。

| シャクヤク | |
| 草丈 | 約60~100cm |
| 開花時期 | 5月〜6月 |
| 花色 | 白、ピンク、赤、紫、黄など |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地にも適応) |
| 耐暑性 | 普通(夏は風通しと水はけを良くする) |
| 管理のしやすさ | 中程度(植え替えの時期・深さに注意) |
豪華な花姿で知られるシャクヤクは、寒冷地でも育てやすい代表格の一つです。むしろ、暖地よりも寒冷地の方が開花が安定しやすいとも言われています。植え付けの深ささえ注意すれば、長く楽しめる多年草です。

| ギボウシ(ホスタ) | |
| 和名 | ギボウシ(擬宝珠) |
| 草丈 | 約20〜80cm(品種により小型〜大型まで幅広い) |
| 開花時期 | 6〜8月 |
| 花色 | 白、薄紫など |
| 耐寒性 | 強い(寒冷地でも越冬可能) |
| 耐暑性 | 普通(高温多湿にはやや注意) |
| 注意点 | 冬は葉が枯れる |
葉の美しさを楽しむホスタは、夏の強い日差しが苦手ですが、冷涼な地域では元気に育ちます。品種によって葉の模様や大きさも様々で、シェードガーデンに最適です。初夏にはすっきりとした花も咲かせます。

| デルフィニウム | |
| 和名 | オオヒエンソウ(大飛燕草) |
| 草丈 | 約50〜200cm(高性品種が多い) |
| 開花時期 | 5〜7月(品種によっては秋にも開花) |
| 花色 | 青、紫、白、ピンクなど |
| 耐寒性 | 強い |
| 耐暑性 | やや弱い(高温多湿に注意) |
| 管理のしやすさ | 中程度(支柱が必要な場合あり) |
涼しい気候を好むデルフィニウムは、寒冷地でこそ本来の力を発揮する花です。空に向かってすっと伸びる花穂が特徴で、ブルー系の花色が特に人気です。夏の高温多湿が苦手なので、冷涼な地域では育てやすい品種です。
これらの宿根草は、いずれも寒さに強く、地上部が枯れても根が生き残って翌年また花を咲かせます。植えっぱなしでも長く楽しめるのが魅力なので、寒冷地での庭づくりに取り入れてみてはいかがでしょうか。
宿根草花壇のレイアウト
宿根草を使った花壇づくりでは、見た目の美しさだけでなく、手入れのしやすさや長期的なバランスも考慮することが大切です。ポイントを押さえてレイアウトを工夫することで、季節ごとに違った表情を楽しめる花壇になります。
まず、草丈による配置を意識しましょう。背の高い植物は花壇の奥や中心に配置し、低い植物は手前に植えることで全体が見渡しやすくなります。例えば、背景にはデルフィニウムやルピナス、中段にはエキナセアやラベンダー、手前にはヒューケラやリシマキアなどがおすすめです。
また、開花時期が異なる品種を組み合わせることで、長く花を楽しめる花壇になります。春に咲くシャクヤクやシバザクラ、夏に見頃を迎えるガウラやルドベキア、秋に花を咲かせるアスターなどを組み合わせると、季節ごとに変化が感じられます。
色のバランスも重要です。単色でまとめるとシックな印象に、補色や類似色を組み合わせると華やかさが引き立ちます。ただし、色数が多すぎると雑然とした印象になるため、3〜4色程度に抑えると調和がとれやすくなります。
最後に、メンテナンス面も意識しておきましょう。広がりやすい品種やこぼれ種で増える植物は、植えるスペースを余裕を持って確保しておくと、後々の管理が楽になります。
このように、高さ・色・開花時期・管理のしやすさを踏まえて宿根草を配置すると、見栄えもよく、長く楽しめる花壇をつくることができます。
花壇の宿根草と低木を使った配置例
宿根草と低木を組み合わせることで、花壇は立体感のある美しい景観に仕上がります。どちらも多年にわたって楽しめる植物のため、計画的に配置することで手間を減らしつつ季節の移ろいを感じられる庭づくりが可能になります。
まず、花壇の後方や中心には背の高い低木を配置しましょう。例えば、アナベル(アジサイの一種)やコデマリのように自然な丸みを持つ低木は、背景としての役割を果たしつつ、花壇に柔らかな輪郭を加えます。
中段には、ボリューム感のある宿根草を。シャクヤクやルピナス、エキナセアなどは高さが中程度で、花壇のアクセントになります。これらは開花時期も比較的長く、色彩も豊かなので華やかな印象を与えてくれます。
手前にはヒューケラやリシマキアのような、葉の模様や色が楽しめるローメンテナンスの宿根草を選ぶと、足元が締まり、全体が安定感のある見た目になります。特にヒューケラはカラーリーフとしても人気で、花が咲かない時期でも彩りを保ってくれます。
このとき注意したいのは、日照条件や風通しなどの環境に合った植物選びです。また、植えた直後はバランスが取りづらく見えるかもしれませんが、数年かけて成長することを前提に余裕を持って配置しておくと、美しくまとまりやすくなります。
このように、宿根草と低木を立体的に配置することで、季節を通して表情豊かな花壇をつくることができます。自然の流れを感じられるような配置を心がけると、手入れも楽しみに変わっていくでしょう。
植えて良かった宿根草の実例紹介
ここでは、実際に植えた人から高評価を得ている宿根草の具体例をご紹介します。
植えてはいけない宿根草を選ばないための注意点まとめ
- 繁殖力が強すぎる植物は花壇全体を侵食する
- 地下茎で広がるタイプは制御が難しい
- 想定以上に大きくなる品種は周囲の植物の成長を妨げる
- 病害虫を呼びやすい宿根草は他の植物にも悪影響を与える
- 冬に地上部が枯れるタイプは見た目が寂しくなる
- 開花期間が短く長期間景観を楽しめないことがある
- 日本の気候に合わない品種は育ちにくく枯れやすい
- 外来種は野生化して地域の生態系を乱すリスクがある
- 放置すると増殖する外来種は近隣にも被害が及ぶ
- 花が終わった後の手入れが必要な品種は油断すると見栄えが悪くなる
- こぼれ種で思わぬ場所に広がる品種は計画的な配置を崩す
- 風通しの悪い場所に合わない植物は病気の原因になる
- 高温多湿に弱い品種は日本の夏に不向き
- 落葉や枯れた茎葉が残ることで庭が雑然と見える
- 人気や見た目だけで選ぶと手入れに苦労する可能性がある