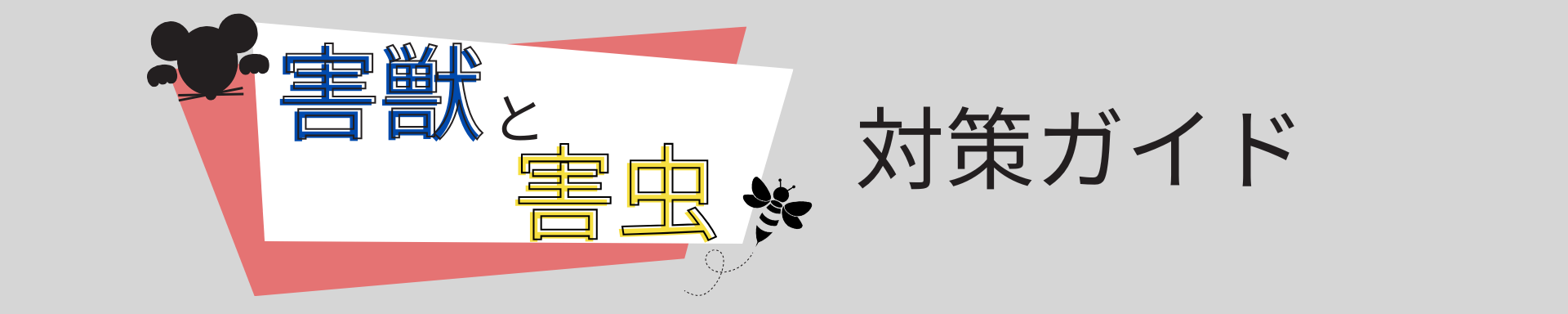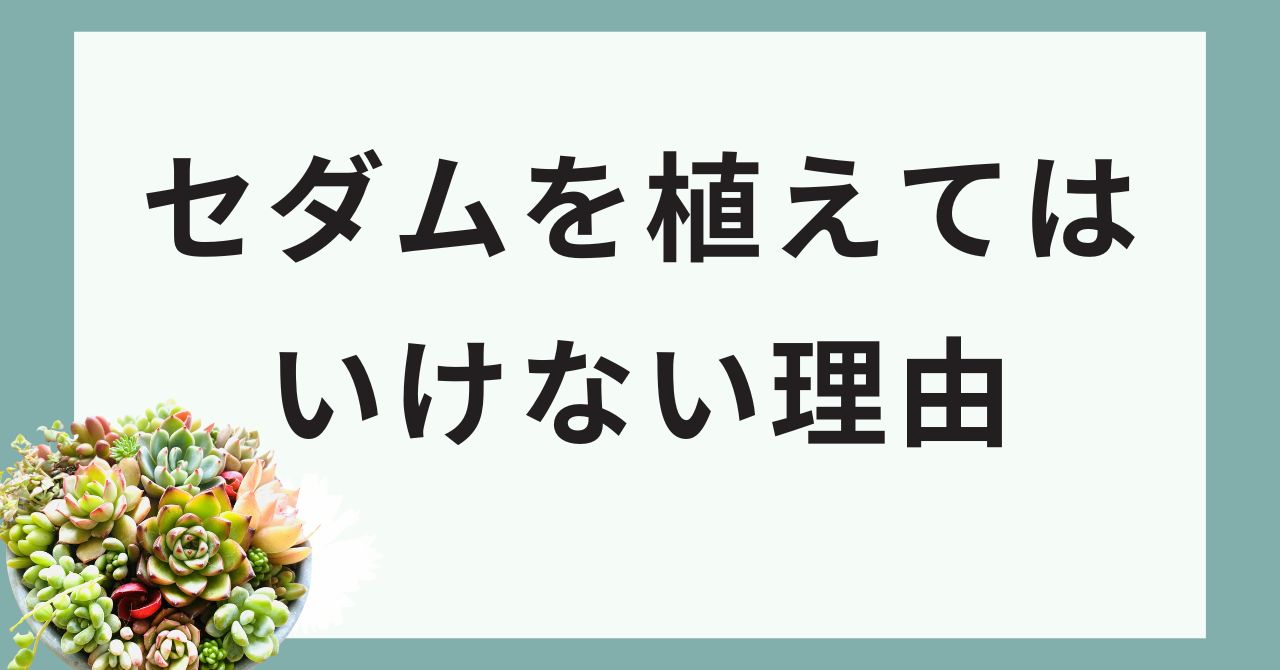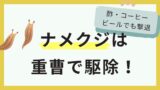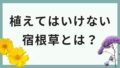セダムは多肉植物の中でも特に人気が高く、グランドカバーや寄せ植え、おしゃれな鉢植えに活用できることから、園芸初心者にも選ばれやすい植物です。しかし最近、「セダム 植えてはいけない」と検索する方が増えています。それは、思った以上に広がってしまったり、地植えで後悔したという声が多いためです。
この記事では、セダムを地植えする際に知っておきたいリスクや、人気ランキングから選ぶおすすめ品種、寄せ植えとの相性、育て方の基本(鉢植え・室内)、さらに増やし方や植え替えの適切な時期まで、幅広く情報をまとめました。これからセダムを取り入れたいと考えている方はもちろん、すでに育て始めて悩みが出てきた方にも役立つ内容となっています。
セダムを植えるかどうか迷っている方が、後悔しない選択ができるよう、わかりやすく丁寧に解説していきます。
- セダムを地植えにした際に後悔する具体的な理由
- 増えすぎを防ぐための対策と管理方法
- セダムの適切な育て方や植え替えの時期
- 寄せ植えやグランドカバーとしての適切な使い方
セダムを植えてはいけない理由とは?
- セダムの基本情報
- セダムの地植えで後悔するケース
- セダムをグランドカバーに使う際の注意点
- グランドカバーとしての代替植物
- 増やし方と時期による繁殖リスク
- セダムの挿し木のやり方
- 知らないと困る増えすぎ対策
セダムの基本情報

| 分類 | 多肉植物(ベンケイソウ科マンネングサ属) | |
| 草丈 | 約2cm〜60cm(品種により異なる) | |
| 生育型 | 春秋型(春と秋に活発に成長) | |
| 日照条件 | 日なたを好むが、夏の直射日光は避けた方が無難 | |
| 耐寒性/耐暑性 | 多くの品種は寒さ・暑さに比較的強い | |
| 適温 | 5〜25℃(品種によっては−5℃程度まで耐えるものもあり) | |
| 水やり | 土が乾いてから(春秋:2〜3日に1回、夏冬:月1〜2回が目安) | |
| 開花時期 | 初夏〜秋(黄色・白・ピンクなどの花を咲かせる品種も) | |
| 用途 | 寄せ植え、グランドカバー、ロックガーデン、ハンギングなどに最適 | |
セダムは、ベンケイソウ科に属する多肉植物の一種で、世界中に400種類以上の品種が存在しています。日本では「万年草(マンネングサ)」という名前で親しまれており、庭やベランダでの栽培にも適した植物です。
セダムの最大の特徴は、その丈夫さと育てやすさにあります。乾燥に強く、葉の内部に水分を蓄える性質を持っているため、水やりの頻度が少なくても元気に育ちます。また、直射日光にもよく耐えるため、屋外での地植えやグランドカバーとしても活躍しています。
葉の形や色もバリエーションが豊かで、緑・黄・赤・ピンクなどカラフルな見た目を楽しめます。品種によっては紅葉するものや、花を咲かせるものもあり、季節ごとの変化を味わうことができるのも魅力のひとつです。

ただし、セダムは繁殖力が非常に強いため、育て方によっては想定以上に広がることがあります。このため、植える場所や管理方法には注意が必要です。
このように、セダムはガーデニング初心者にも育てやすく、見た目の可愛らしさと実用性を兼ね備えた多肉植物です。特に、手間をかけずに緑を楽しみたい方にとっては、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。
セダムの地植えで後悔するケース
セダムは丈夫で手間のかからない多肉植物ですが、地植えにした際に「思っていたのと違った」と感じるケースも少なくありません。ここでは、特に注意すべき後悔ポイントを具体的に紹介します。
想像以上に広がりすぎる
セダムは横に這うように成長し、落ちた葉や茎の一部からでも簡単に根付きます。そのため、何もしなくても面積がどんどん広がっていくことがあります。1株だけ植えたつもりが、1年後には隣の植物を覆ってしまうことも。特に境界を設けていない庭ではコントロールが難しくなります。
他の植物の日照を奪う
地表を覆うように成長するセダムは、草丈の低い植物や苗のスペースを奪ってしまうことがあります。これにより、光が当たらなくなった植物が育たなくなるなどのトラブルが起こる可能性もあります。
踏みつけに弱い
セダムは芝生のような用途で期待されることもありますが、実際は人の出入りが多い場所には不向きです。茎や葉が傷むと、傷口から腐敗しやすくなります。見た目が悪くなるだけでなく、広がった箇所全体が傷む原因になることもあります。
害虫の住処になりやすい
セダムが密集して育つことで、ナメクジやダンゴムシなどの虫が住みつきやすくなります。特に湿気が多い場所では、雑草が生えるよりも先に虫害が発生することがあります。清掃が行き届かない場所や水はけの悪い場所では注意が必要です。
このようなケースを事前に理解しておくことで、セダムの地植えをより安全に、効果的に楽しむことができます。適度に管理できるスペースや植え方を考えて取り入れることが、後悔を防ぐコツといえるでしょう。
セダムをグランドカバーに使う際の注意点
セダムは丈夫で見た目も美しく、手間がかかりにくい植物としてグランドカバーに選ばれることが多いです。ただし、使い方を誤ると後悔することにもつながるため、以下のポイントに注意しましょう。
水はけの悪い場所は避ける
セダムは乾燥には強い一方で、湿気に弱い特徴があります。長雨や湿った場所に植えると、根腐れやカビが発生しやすくなります。植える場所は必ず水はけの良い場所を選ぶようにしましょう。
踏まれやすい場所には不向き
芝生とは異なり、セダムは踏みつけに耐える構造ではありません。茎や葉が潰れると傷んでしまい、回復に時間がかかることもあります。人が歩く場所や通路には植えないようにするのが安全です。
増えすぎに注意する
セダムは一部がこぼれ落ちるだけで簡単に根付き、あっという間に広がっていきます。予期せぬ場所に広がるのを防ぐためにも、レンガや縁石などで物理的な境界を作るのが効果的です。
他の植物を圧迫する可能性がある
成長スピードが早いため、他の植物のスペースにまで侵入してしまうことがあります。混植する際は、ゆっくり成長する植物や根張りの浅い植物を選ぶなど、種類同士の相性を意識して配置しましょう。
季節ごとのメンテナンスを忘れずに
夏場は蒸れやすくなるため、密集しすぎた部分を間引くなどの管理が必要です。また、冬は寒さに弱い品種があるため、霜よけや室内への移動なども検討しましょう。
このように、セダムをグランドカバーとして取り入れる際は、その特性に合わせた細かな配慮が求められます。適切な環境と管理を心がければ、長く美しい状態を保つことができます。
グランドカバーにおすすめの代替植物
セダムの代わりにグランドカバーとして活用できる植物は、管理のしやすさや見た目の違いによって多種多様にあります。ここでは、庭の雰囲気に合った代替植物を選ぶために、代表的な種類とその特徴を紹介します。
タイム

タイムは、香りが楽しめるハーブとしても人気がありながら、地面を這うように広がるため、グランドカバーにも向いています。踏みつけに強く、小道の縁や花壇の隙間にもよく利用されます。春には紫やピンクの小さな花を咲かせ、見た目にも楽しめます。
リシマキア・ヌンムラリア

リシマキアは、ライムグリーンやダークブロンズなど葉色が美しい種類があり、庭に彩りを加えたいときに便利です。湿気に強く、日陰でも育てやすいため、日当たりに不安のある場所でも活躍します。
ダイカンドラ(ダイコンドラ)

ダイカンドラは丸い小さな葉が密集して広がり、芝生代わりとして使われることもあります。乾燥にも比較的強く、管理の手間も少ないため、ナチュラルガーデン風に仕上げたい方におすすめです。
ヒメイワダレソウ(リッピア)

ヒメイワダレソウは繁殖力が高く、短期間で地面を覆ってくれます。小さな白やピンクの花を咲かせるため、花の彩りを楽しみたい方にもぴったりです。踏圧にも強く、歩道沿いや駐車場の縁などにも使用できます。
グレコマ(カキドオシ)

グレコマは葉に斑が入る独特な見た目で、日陰にも強いのが魅力です。繁殖力があるため、定期的な剪定は必要ですが、雑草抑制効果も期待できます。和風・洋風どちらの庭にもなじみやすい植物です。
このように、グランドカバー植物にはそれぞれ特徴があります。増えすぎを懸念する場合や、環境に合った種類を選びたい場合は、セダム以外の選択肢も積極的に検討するとよいでしょう。植える場所の条件に合わせて適した植物を選ぶことが、美しい庭づくりへの第一歩です。
増やし方と時期による繁殖リスク
セダムは手軽に増やせることで知られていますが、増やし方や時期を誤ると、思いがけず庭全体に広がってしまうリスクがあります。特に地植えの場合は注意が必要です。
挿し木や葉挿しは成功率が高い
セダムの増やし方として一般的なのが「挿し木」や「葉挿し」です。茎や葉を切って土の上に置くだけで根を張ることもあり、増やすのは非常に簡単です。特別な技術も必要ないため、初心者でも手軽に取り組めます。ただし、この増やしやすさが繁殖リスクと背中合わせである点には注意しましょう。
挿し木の準備手順
挿し木を行うには、まず健康なセダムの茎を用意します。次の手順に従って準備をしましょう。
- カット:5~10cmほどの長さで、元気な茎を清潔なハサミでカットします。
- 下葉の処理:切った茎の下部に付いている葉は、1~2cm程度取り除きます。これにより、土に挿したときの腐敗を防ぐことができます。
- 乾燥:切り口はすぐに土に挿さず、風通しのよい日陰で2~3日乾燥させましょう。切り口が乾くことで、病気や腐敗のリスクを減らすことができます。
土への挿し方と管理
準備が整ったら、乾燥した茎を水はけのよい土に挿します。多肉植物専用の培養土や、赤玉土・鹿沼土をブレンドした用土が適しています。
- 挿す深さ:土に対して1~2cmほど挿すのが目安です。あまり深く挿しすぎると、茎が蒸れて腐ることがあります。
- 水やり:挿した直後は水を与えず、1週間ほどは乾燥した状態で管理します。根が出始めたら、土が乾いたタイミングで軽く水を与えるようにしてください。
- 置き場所:明るい日陰が理想です。直射日光は避け、風通しのよい場所で育てましょう。
発根までの目安期間
品種や環境によって異なりますが、1~3週間ほどで発根します。葉がしっかりと土を押さえるようになったら、少しずつ日当たりの良い場所に移していきましょう。
春と秋は増えやすいシーズン
3〜5月、または9〜10月の生育期は、セダムが活動的な時期であり、発根もしやすくなります。この時期に剪定や挿し木を行うと、短期間で新たな株が育っていくため、管理が行き届かないと一気に範囲が広がる可能性があります。
思わぬ場所から増殖するケースも
セダムは小さな葉や茎が土の上に落ちただけでも根を張ることがあります。特に靴底に付着したり、風で飛ばされた断片が意図しない場所で根付くこともあり、気づいたときには他の植物のスペースを圧迫していることも珍しくありません。
増やすときは場所と管理方法を慎重に
鉢植えであれば増えすぎのリスクはある程度コントロールできますが、地植えの場合は境界をしっかりと作るなどの対策が必要です。また、増やす予定がない場合は、剪定後の茎や葉を土の上に放置しないことも重要です。
知らないと困る増えすぎ対策
セダムは手間がかからず育てやすい一方で、環境が整うと驚くほど勢いよく広がる植物です。特に地植えやグランドカバーに利用する場合、何も対策をしなければ庭の予定外の範囲まで拡大してしまうことがあります。ここでは、セダムの「増えすぎ問題」に対処するための具体的な方法をご紹介します。
境界をレンガや仕切りで明確にする
まず最も基本的な対策が、物理的な境界を設けることです。セダムは地面を這うように広がっていくため、レンガ・ブロック・ガーデンフェンスなどで囲うことで侵入を防げます。とくに芝生や他の植物との混在を避けたいときは有効です。
鉢やプランターを活用して管理する
広がる力をコントロールしたい場合、鉢植えでの栽培がもっとも確実な方法です。特にテラスやベランダで育てる場合、限られたスペースで管理しやすく、好きな場所に移動できる点もメリットです。また、プランター内で寄せ植えを楽しむことで、見た目もおしゃれに仕上がります。
定期的に間引き・剪定をする
増えすぎたセダムは、定期的に剪定することで広がりを抑えることができます。春と秋の生育期に合わせて、伸びた茎をカットしたり、密集している部分を間引いたりすることで、通気性を保ちつつ美しい形を維持できます。
地面に直接植えた場合は「根ごと除去」
セダムは茎だけでなく、落ちた葉からでも簡単に根付いてしまいます。そのため、不用意に放置した切れ端から再生するリスクもあります。完全に取り除きたい場合は、根ごと丁寧に掘り返す必要があります。特にメキシコマンネングサなどの繁殖力が強い品種は要注意です。
普段の靴底にも注意
意外と見落とされがちなのが、靴底に付いた葉や茎の断片による拡散です。庭作業のあとに気づかぬうちに他の場所へ運んでしまい、そこから増えてしまうこともあります。作業後は靴底を軽くチェックすると、知らぬ間の「越境セダム」を防げます。
このように、少しの対策でセダムの増えすぎは十分にコントロール可能です。管理を怠らず、定期的に状態をチェックしながら育てていきましょう。
セダムは植えてはいけない訳じゃない!育て方のコツ
- セダムの人気ランキング
- 鉢植えでの育て方と管理方法
- 室内での育て方と注意点
- セダムの植え替え時期
- 寄せ植えでの相性が良い植物は?
セダムの人気ランキング
セダムは品種が非常に多く、見た目や育て方の違いから、それぞれにファンがついています。ここでは、初心者から上級者まで多くの人に人気のあるセダムをランキング形式でご紹介します。園芸店やネットショップで取り扱いの多いものを中心にまとめています。
第1位:虹の玉(にじのたま)

虹の玉は、セダムの中でも特に知名度が高い品種です。ぷっくりと丸い葉が美しく、秋には赤く紅葉することで、季節の変化を楽しめます。育てやすく、挿し木で簡単に増やせるため、多肉植物初心者にもおすすめです。
第2位:乙女心(おとめごころ)

かわいらしい名前にぴったりな、葉先がほんのりピンクに染まる上品なセダムです。葉はやや白っぽく粉をふいたような質感があり、寄せ植えにアクセントを加えたいときに便利です。耐寒性もあり、年間を通して楽しめます。
第3位:オーロラ

オーロラは、ピンクと緑のグラデーションが特徴の華やかなセダムです。見た目の美しさから、特に女性人気が高く、リースや鉢植えにもよく使われています。ただし、やや暑さに弱いため、夏の管理には注意が必要です。
第4位:春萌(はるもえ)
春萌は、明るいライムグリーンの葉が印象的で、春に黄色の花を咲かせる品種です。肉厚で丈夫なため、挿し木でも簡単に増やせます。鉢植えでも地植えでも育てやすい万能タイプです。
第5位:玉つづり(たまつづり)
「ビアホップ」という別名もある玉つづりは、葉がぎっしりと詰まったつる性のセダムで、吊り鉢やハンギング向きとして大変人気です。成長すると重みで自然に垂れ下がり、ボリュームのある姿になります。
第6位:トリカラー

トリカラーは、緑・ピンク・白の三色の葉が魅力の斑入りセダムです。暑さ寒さにも比較的強く、寄せ植えや地植えでも映えるため、ガーデンデザインにも重宝されます。明るい色合いが庭を華やかに彩ってくれます。
このように、セダムはそれぞれの品種に個性があり、見た目だけでなく育てやすさや使い方にも違いがあります。まずはお気に入りのひとつを選び、そこから少しずつコレクションを増やしていくのも楽しいですよ。
鉢植えでの育て方と管理方法

セダムを鉢植えで育てることで、スペースの少ないベランダや室内でも管理しやすくなります。特に地植えでは広がりすぎてしまうリスクがあるため、限られた範囲で楽しみたい方には鉢植え栽培が適しています。ここでは、鉢植えでセダムを育てる際の基本的な方法と、注意点について解説します。
適した鉢の選び方
セダムは水はけの良い環境を好むため、底に排水穴がある鉢を選ぶのが基本です。素焼きの鉢は通気性がよく、根腐れのリスクも軽減できます。おしゃれなプラスチック鉢でも問題ありませんが、蒸れやすくなることもあるため、水やりに注意が必要です。
土の選び方と準備
用土は市販の多肉植物専用培養土が最適です。自作する場合は「赤玉土(小粒)」「鹿沼土」「腐葉土」などを1:1:1で混ぜ、排水性を高めましょう。また、鉢底には必ず鉢底石を敷いておくと、過湿を防ぎやすくなります。
日当たりと置き場所
セダムは日光を好む植物なので、春から秋にかけては直射日光の当たる屋外がベストです。ただし、真夏の強光では葉焼けすることもあるため、遮光ネットや半日陰に移すことで葉の傷みを防げます。冬は霜に弱い品種もあるため、室内の窓辺で管理するのが安全です。
水やりのタイミング
水やりは、鉢の土が完全に乾いてからが基本です。春と秋の生育期は3日に1回程度、鉢底から水が流れるくらいたっぷりと与えます。一方で夏と冬の休眠期には水やりの回数を減らし、月に1〜2回程度の軽い水やりで十分です。
肥料の与え方
セダムはもともと肥料をあまり必要としません。春と秋に、月1回程度の液体肥料を薄めて与える程度でOKです。それ以外の時期に与えると、かえって根を傷める「肥料焼け」のリスクが高まるため注意しましょう。
定期的な剪定と植え替え
成長が早いセダムは、放っておくと徒長して見た目が悪くなります。形を整えるために、春か秋に軽く剪定してあげると、美しい株姿が保てます。また、1〜2年ごとに植え替えを行うことで、根詰まりや土の劣化を防ぎ、健康な状態を維持しやすくなります。
鉢植えの管理は、セダムの増えすぎを防げるだけでなく、移動や剪定がしやすい点でもメリットがあります。丁寧な観察と適切な環境調整で、長く美しいセダムを楽しむことができます。
室内での育て方と注意点

セダムは屋外栽培が基本ですが、室内でも育てることができます。特に寒冷地や、日中の外出が多く水やり管理が難しい方には、室内栽培が適している場合もあります。ただし、環境によってはうまく育たないこともあるため、育て方のポイントと注意点を押さえておきましょう。
日当たりの確保が最重要
セダムは日光をしっかりと浴びることで健康に育つ植物です。そのため、室内で育てる場合は「南向きの窓辺」など、日当たりの良い場所を選んでください。最低でも1日に4〜6時間は光が当たる環境が理想的です。日照不足になると、茎が間延びしたり、葉が落ちたりする「徒長」が起こる可能性があります。
室内の空気環境に注意
風通しが悪い部屋では、湿気がこもって蒸れやすくなります。これはセダムにとって大きなストレスとなり、根腐れやカビの原因になることもあります。できれば定期的に換気を行い、扇風機やサーキュレーターで空気を循環させる工夫をしましょう。
水やりの回数を減らす
屋外よりも乾燥しにくい室内では、水やりの頻度を抑えることが大切です。春と秋の生育期でも、土の表面が完全に乾いてからさらに1〜2日置いて水を与える程度で十分です。冬は休眠期になるため、月に1回ほどの軽い水やりで問題ありません。鉢の受け皿に水が溜まらないように注意しましょう。
冬の管理は室温と乾燥に配慮
冬場は暖房によって空気が乾燥しがちです。暖房機器の吹き出し口付近や、直射的な温風が当たる場所には置かないようにしてください。また、暖房が効いていない室内では5℃を下回らないように管理する必要があります。室温が不安定な場合は、簡易的な温室ケースの使用も検討しましょう。
病害虫の早期発見がカギ
室内で育てていると、ハダニやカイガラムシといった害虫がつくことがあります。葉の表や裏を定期的に観察し、小さな変化に気づくことが大切です。もし異常を見つけたら、ピンセットで取り除く、もしくは園芸用の殺虫剤を使って対処しましょう。
このように、室内でもセダムは十分に育てられますが、日光と通気の管理には特に注意が必要です。環境を整えることで、コンパクトながらも美しい姿を長く楽しむことができます。
セダムの植え替え時期

セダムは比較的育てやすい多肉植物ですが、植え替えのタイミングを間違えると、根が傷んだり生育が遅れたりする原因になります。元気に育て続けるためには、適切な時期に植え替えを行うことが重要です。
ベストな植え替え時期は春と秋
セダムの植え替えに適しているのは、気温が安定して過ごしやすい「春(3月〜5月)」と「秋(9月〜10月)」です。これらの時期はセダムの生育が活発になるタイミングでもあるため、植え替え後に根がダメージを受けても、比較的早く回復しやすくなります。
また、植え替えが必要になる目安としては、以下のような状態が見られるときです。
- 鉢の底から根が出ている
- 水の吸い込みが極端に悪くなった
- 茎や葉が極端に徒長している
- 鉢の中で株がぐらつく
このようなサインがあれば、季節を問わず植え替えを検討する価値がありますが、可能であれば上記の「春・秋」を待つようにしましょう。
夏と冬の植え替えは避ける
夏の高温期や冬の低温期は、セダムが休眠または生育が鈍くなる時期です。この時期に植え替えを行うと、根がうまく張らなかったり、ストレスから枯れてしまうことがあります。やむを得ない場合を除き、これらの時期の作業は避けるようにしてください。
植え替えの頻度は1〜2年に1回が目安
セダムは生育が早い種類が多く、鉢の中がすぐに窮屈になってしまうこともあります。1年に1回程度の植え替えを心がけると、常に新しい土と十分なスペースで健康的に育てることができます。特に寄せ植えをしている場合は、他の植物とのバランスも見ながら植え替えのタイミングを調整すると良いでしょう。
このように、セダムの植え替えは時期選びが大きなポイントになります。適切な季節に、株の状態を見ながら無理のないタイミングで作業を進めることが、長く美しい姿を保つコツです。
寄せ植えでの相性

セダムは種類が豊富で色や形もさまざまなため、寄せ植えのアクセントとして非常に使いやすい植物です。ただし、相性の良い植物を選ぶことが、寄せ植えを美しく保つコツでもあります。
同じ生育環境を好む植物が基本
まず押さえておきたいのは、「セダムと同じような環境で育つ植物」を選ぶことです。セダムは乾燥に強く、日当たりと水はけの良い場所を好みます。したがって、多肉植物やサボテンなど、乾燥に強い品種と相性が良いです。
相性の良い植物の例
エケベリア

ロゼット状に葉を展開する美しい多肉植物で、セダムと並べると立体感が出ます。カラーバリエーションも豊富なので、寄せ植えに彩りを加えられます。
クラッスラ(金のなる木)

成長の仕方が品種によって異なり、直立型や這うタイプがあります。セダムと組み合わせることで高低差を生み出し、リズムのあるデザインが可能になります。
グラプトペタルム

厚みのある葉が特徴で、淡い色合いがセダムとよく馴染みます。寄せ植え全体の印象を柔らかくまとめてくれる役割を担います。
リトープスやコノフィツム


石に似た外見を持つ個性的な多肉植物。セダムの柔らかい印象と対照的な質感が面白いコントラストになります。
色と形のバランスも大切
寄せ植えでは見た目のバランスも重要です。セダムの中には「虹の玉」や「オーロラ」のように赤く色づくもの、「タイトゴメ」や「黄金丸葉万年草」のように明るい黄緑色の品種もあります。色のグラデーションや葉の大きさを意識して組み合わせると、見映えの良い寄せ植えになります。


避けたほうが良い植物
一方で、水を多く必要とする観葉植物や、日陰を好む草花は、セダムとの相性が悪くなります。セダムの育成条件に合わない植物を混植すると、どちらかが枯れる可能性があるため避けましょう。
このように、寄せ植えでは「育成条件の一致」と「色・形の調和」がポイントになります。センスを活かしながら、育てやすさも考慮して植物を選びましょう。
セダムを植えてはいけないと言われる理由と対策まとめ
- セダムは繁殖力が非常に強く、地植えで予想外に広がる
- 他の植物のスペースや日照を奪うことがある
- 踏みつけに弱く、人の往来が多い場所には不向き
- 密集しやすく、害虫の住処になりやすい
- 地植えでは境界を設けないと隣のエリアに侵入しやすい
- 挿し木や葉挿しで簡単に増えるため、管理が甘いと広がる
- 増えた断片が靴底や風で運ばれ、予期せぬ場所で根づく
- 増えすぎ防止にはレンガや縁石で物理的に仕切るとよい
- セダムは乾燥に強いが湿気に弱く、水はけの悪い場所は避ける
- 繁殖力のある品種は特に注意が必要である
- 鉢植えなら管理がしやすく、増えすぎを防ぎやすい
- 室内で育てる場合は日照と通気を確保することが重要
- 植え替えは春か秋が最適で、夏冬は避ける
- セダムは寄せ植えで相性の良い多肉植物と合わせると映える
- グランドカバーにはタイムやリシマキアなど代替植物も選択肢に入る