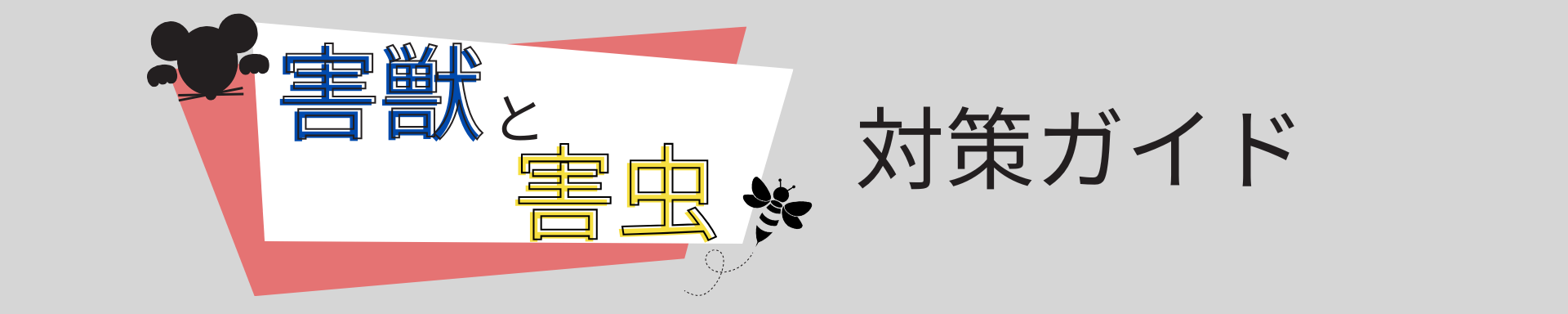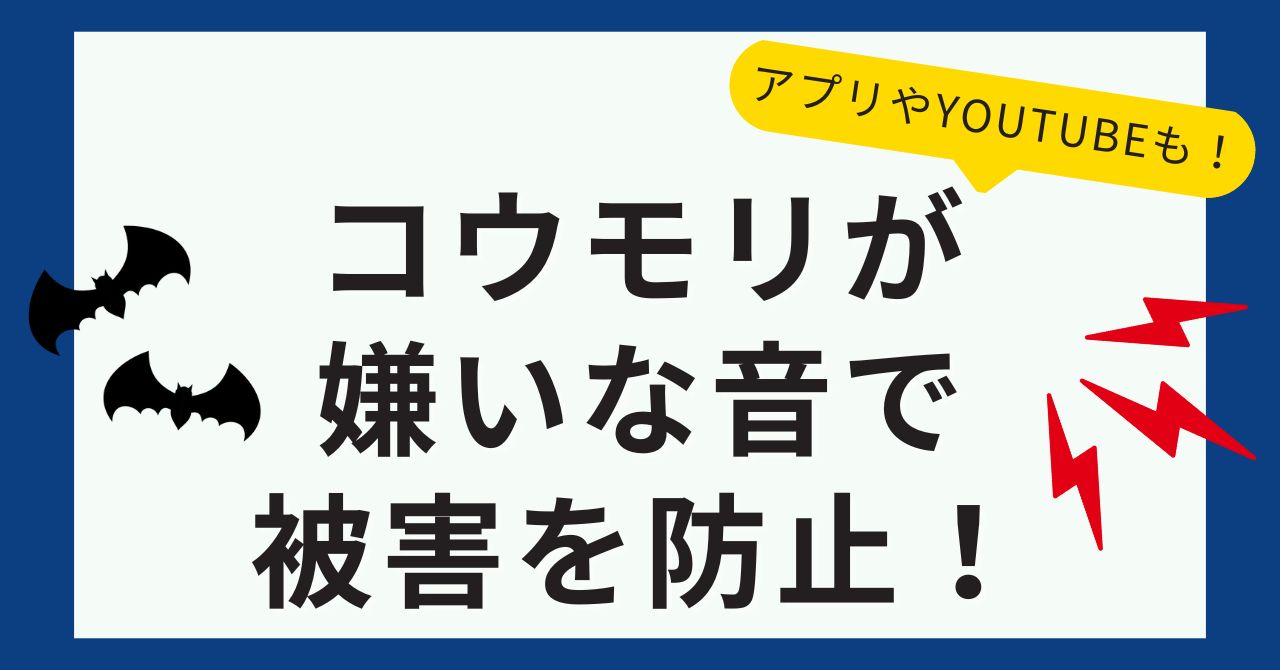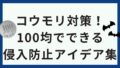自宅の屋根裏や軒下から聞き慣れない音がしたとき、「もしかしてコウモリ?」と心配になったことはありませんか。
特に夜間に「キィキィ」「バサバサ」といった音が聞こえると、不安を感じる方も多いはずです。「コウモリ 嫌いな音」で検索する人の多くは、そうした状況に悩まされ、効果的な対策を探しているのではないでしょうか。
本記事では、コウモリが本能的に避ける音や環境に注目し、モスキート音や高周波のような「嫌がる音のYouTube」、さらに嫌いな音が出るアプリを使ったスマホでの対策まで詳しく解説しています。また、コウモリがライトを苦手な理由や、嫌いな色、嫌がるものについても紹介します。
コウモリがどんな音を嫌うのか、どんな対策が現実的なのかを知りたい方に向けた、実践的な情報が満載です。コウモリを寄せつけないための第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。
- コウモリが嫌がる音の具体例と特徴
- 音を使った対策方法とその効果の違い
- モスキート音やアプリを使った予防方法
- 音以外の光やにおいを使った忌避方法
コウモリが嫌いな音で対策する方法
- コウモリが居るとどんな音がする?
- コウモリが嫌がるものとは?
- YouTubeで嫌がる音を出してみる
- モスキート音の効果
- コウモリに効く?嫌いな音を出すアプリ
コウモリが居るとどんな音がする?

コウモリが家の中やその周辺にいると、独特な音が聞こえることがあります。これは私たちが気づくための大きな手がかりにもなります。
キィキィ、チューチューといった高音が特徴
コウモリの鳴き声は、一般的に「キィキィ」や「チューチュー」といった高めの音で、人によってはネズミの鳴き声と勘違いすることもあります。特に静かな夜間には響きやすく、天井裏や壁の中から聞こえることが多いです。
バサバサという羽音にも要注意
羽を広げて飛ぶときの音も見逃せません。狭い屋根裏や壁の隙間を移動するときには「バサバサ」と羽ばたく音や、「コソコソ」と何かが擦れるような音が聞こえることもあります。これらは昆虫や鳥とは違った、乾いたような羽音が特徴です。
時間帯は夕方から夜にかけてが多い
夜行性であるため、音が聞こえる時間帯にも特徴があります。日没後の静かな時間帯に、音が増えるようであればコウモリの可能性が高いといえるでしょう。また、活動の始まりである夕方ごろに屋根裏などから一斉に出ていく気配を感じることもあります。
音が小さくても油断は禁物
コウモリの動きや鳴き声は非常に小さいことが多く、聞き逃してしまうこともあります。しかし、日々の生活の中で「いつもと違う音」が気になったら、一度静かな時間帯に耳を澄ませてみると発見につながるかもしれません。
このように、コウモリの存在は鳴き声や羽音で知ることができます。気になる音を感じたら、その場所を丁寧に点検し、早めの対処を検討しましょう。
コウモリが嫌がるものとは?

コウモリを家に寄せ付けないためには、彼らが本能的に避ける「嫌がるもの」を活用するのが効果的です。いずれも簡単に試せる方法が多く、日常の中で取り入れやすい対策となります。
強いにおい(ハッカ・ナフタリンなど)
コウモリは嗅覚が敏感で、強いにおいを特に嫌がります。たとえばハッカ油やミント系の香り、防虫剤に含まれるナフタリンなどが苦手です。スプレーにして散布する、もしくはコットンに染み込ませて出入口付近に置くだけでも、近寄りにくくなります。
明るい光
夜行性のコウモリは、暗く静かな場所を好むため、強い光を嫌います。センサーライトや常夜灯を設置すると、安心できない環境と判断して避けるようになります。特に、侵入経路になりやすい軒下や換気口付近のライトが有効です。
高周波や超音波
コウモリは超音波で周囲を認識しているため、一定の周波数の音を発する機器も効果があるとされています。ペットボトルを使った簡易音反射装置や市販の害獣対策グッズを使用することで、忌避効果が期待できます。
動くものや天敵のシルエット
風で動く銀色のテープや、フクロウの模型といった「視覚的に警戒させる物」も有効です。天敵が近くにいると錯覚させることで、安心できない場所だと判断させることができます。ただし、慣れやすいため時々場所を変える工夫も必要です。
こまめな人の気配
コウモリは人の気配が少ない場所をねぐらに選びます。物置やシャッター裏なども、こまめに掃除や点検をすることで「安全な隠れ家ではない」と認識させることができ、自然と寄りつかなくなります。
このように、コウモリが嫌がる要素を生活環境に取り入れることで、被害を未然に防ぐことが可能です。いくつかの方法を組み合わせて使うことで、より高い効果が期待できるでしょう。
YouTubeで嫌がる音を出してみる
コウモリ対策として「音」を活用する方法の一つに、YouTubeなどの動画サイトで公開されている“忌避音”を再生するという手段があります。特別な機器がなくてもスマートフォンやスピーカーがあれば試せるため、手軽さが魅力です。
コウモリは高周波を嫌がる傾向がある
コウモリはもともと超音波で周囲を把握する能力を持っており、特定の高周波音に対して強いストレスを感じることがあります。人間には聞こえない周波数でも、コウモリには届いているため、こうした音を活用すれば追い出しやすくなる場合があります。
YouTubeで「コウモリ 忌避音」と検索してみる
YouTubeでは「コウモリが嫌がる音」「超音波 コウモリ対策」などのキーワードで検索すると、忌避を目的とした音声コンテンツが複数ヒットします。音の種類や周波数帯も様々なので、実際に試してみて反応を観察するのがおすすめです。
再生方法と注意点
スピーカーをコウモリが出入りする場所に向けて再生すると、音の影響を受けやすくなります。ただし、周囲の人間やペットにもストレスを与える可能性があるため、音量や再生時間には配慮が必要です。また、効果が一時的な場合もあるため、長時間の連続再生は避けましょう。
効果が薄いと感じたら他の方法も併用を
音による対策はコウモリによって反応が異なることもあり、効き目が実感できないケースもあります。その場合は、光やにおいによる対策、ネットなどと組み合わせて対処することで、より高い忌避効果が期待できます。
このように、YouTubeを利用した忌避音の再生は、コストをかけずに始められる簡易的な対策として有効です。ただし、あくまで「補助的手段」として位置づけ、他の対策と合わせて使うことが望ましいでしょう。
モスキート音の効果

モスキート音とは、高周波の音波で、主に10代から20代の若者にだけ聞こえると言われる特殊な音です。この音を利用してコウモリを遠ざけるというアイデアが注目されることがありますが、実際の効果には限界がある点も押さえておく必要があります。
コウモリにとって不快な周波数帯とは異なることもある
モスキート音の周波数はおおよそ17kHz〜20kHz程度です。一方、コウモリが使うエコーロケーション(超音波)の周波数帯は30kHz以上であることが多く、彼らの感知領域とは完全には一致しません。そのため、モスキート音が直接的な忌避効果を持つとは言い切れないのが現状です。
一部の個体に影響する可能性はある
それでも、コウモリの種類や個体差によっては、モスキート音のような高音に敏感に反応するケースもあります。実際、一定の騒音や音波にストレスを感じて巣を離れる習性があることは知られており、まったく効果がないとは言い切れません。
周囲の人や動物にも配慮が必要
モスキート音は若者やペットにも聞こえる可能性があります。そのため、近所に住む人や犬・猫などへの配慮も欠かせません。長時間にわたって流し続けると、思わぬトラブルにつながることがあるため、使用時間や音量の調整は重要です。
他の対策と併用することで効果アップ
モスキート音だけに頼るのではなく、防虫ネットや忌避スプレー、センサーライトなど他の対策と組み合わせて使用することで、より高いコウモリ対策効果が見込めます。単独での効果は限定的なため、総合的な防除プランの一部として考えるのが現実的です。
このように、モスキート音は「補助的な手段」として活用することが可能です。過度な期待は禁物ですが、少しでもコウモリを寄せつけたくないという方には、試してみる価値のある方法の一つと言えるでしょう。
コウモリに効く?嫌いな音を出すアプリ
スマートフォンを使って手軽にコウモリを遠ざけたいと考えますよね。しかしアプリによっては周波数が合わない場合もあり、効果があるとは言えないようです。
iphone超音波アプリの一例をご紹介
下記アプリでは、15kHz〜20kHz前後の音を再生できる機能があります。コウモリは20kHz~40kHzの範囲の周波数に反応するため、あまり効果がないと考えられます。下記以外の超音波を発するアプリの中には、口コミに「お金を払えという表示ばかり出る」などと書かれているものもあり、あまりおすすめ出来るアプリは見つけることが出来ませんでした。
スマホのスピーカー性能によって差が出る
一般的なスマートフォンのスピーカーでは、超音波や高周波を正確に出力するのが難しい場合もあります。高性能な外部スピーカーや専用デバイスと組み合わせないと、期待した音が十分に再生されないことがあります。
アプリの利用は時間と環境を選ぶ
深夜など静かな時間帯に使用することで、音の効果を高めることができます。一方で、住宅密集地では音が響きすぎたり、人やペットに不快感を与えるおそれもあるため、使用場所や音量の調整には注意が必要です。
他の忌避方法と組み合わせると安心
アプリによる音の対策だけでコウモリを完全に遠ざけるのは難しいこともあります。そのため、網やスプレー、光による対策とあわせて使用することで、総合的な防除効果が高まります。
このように、嫌いな音を出すアプリは、スマホ一つで試せる手軽な方法ですが、効果には限界もあるため、あくまで「補助的な対策」として取り入れるのがおすすめです。
「コウモリが嫌いな音」以外の追い出し方
- コウモリがライトを苦手とする理由
- コウモリが嫌いな色はある?
- コウモリ対策に有効なアイテム
- コウモリを追い出す際の注意点
コウモリがライトを苦手とする理由

コウモリは基本的に夜行性の動物であり、暗闇の中での活動に適した感覚器官を持っています。そのため、明るいライトを極端に嫌う傾向があります。
強い光が目に負担をかける
コウモリの目は暗い環境に特化しており、微弱な光でも周囲を把握できるよう進化しています。逆に言えば、強い光にはとても敏感であり、突然照らされると目がくらんで行動が鈍くなったり、逃げ出したりすることが多くなります。
暗闇での安全確保が難しくなる
彼らは超音波によるエコーロケーション(反響定位)を使って空間を認識していますが、周囲が明るくなると警戒心が高まり、安心して移動や休息ができなくなります。特に静かで暗い場所を求める本能があるため、光があるだけでその場から離れていく可能性が高くなります。
人間の気配を感じやすくなる
ライトが点いているということは、近くに人がいる・活動しているとコウモリが判断する要因にもなります。人間や天敵の気配を察知しやすくなるため、明るい環境はコウモリにとって「危険な場所」と認識されることが多いです。
一時的な対策としても有効
屋根裏や軒下、換気口などにセンサーライトや常夜灯を設置することで、コウモリの侵入や定着を防ぐことができます。特に100均などで手に入るライトを複数活用すれば、手軽に対策を始められるのもメリットです。
このように、ライトがコウモリにとって不快な存在であるのは、彼らの生態や行動習性によるものです。日常的に光を使った環境づくりを意識することで、侵入予防につながります。
コウモリが嫌いな色はある?

コウモリに特定の「嫌いな色」があるかどうかについては、科学的に明確な根拠は少ないのが現状です。とはいえ、彼らの視覚の特徴から、色よりも「光の強さ」や「環境の明暗」のほうが行動に強く影響を与えることがわかっています。
コウモリの視力は明暗を重視している
多くのコウモリは色覚を持たず、視力そのものも人間ほど発達していません。その代わりに、超音波による反響定位で空間を把握し、光の明るさや影を手がかりに移動しています。つまり、色そのものではなく、暗いか明るいかの「明暗差」が行動に影響を与えていると考えられます。
明るい色は避ける傾向がある
一般的に、明るい色や光を反射しやすい物体は、コウモリにとって落ち着かない環境を生みやすくなります。たとえば、白や銀のように光を反射する素材のものは、ねぐらや通り道に適さないと判断される場合があります。
暗い色は潜みやすい環境になる
一方で、黒や濃い茶色など暗めの色は、光を吸収しやすく影をつくりやすいため、コウモリが好んで潜む場所になりやすいです。そのため、建物の外壁や屋根裏などがこうした色合いの場合は、より注意が必要です。
色よりも「環境」を見直すことが重要
色そのものに頼った対策は効果が限定的であるため、コウモリの侵入を防ぐには、明るいライトの設置や音・においによる忌避など、視覚以外の感覚を刺激する方法と組み合わせることが現実的です。
このように、コウモリに「嫌いな色」があるとは断定できないものの、明るい色や光をうまく使うことで、彼らにとって居心地の悪い環境をつくることが可能です。色選びよりも、全体的な空間づくりを意識することが、より効果的な対策につながります。
コウモリ対策に有効なアイテム

コウモリの侵入や定着を防ぐには、彼らの習性を理解したうえで効果的なアイテムを使うことがポイントです。市販で手に入りやすく、実用性のある対策グッズを組み合わせることで、自宅の被害を減らすことが可能になります。
ハッカスプレーや忌避スプレー
コウモリは強い香りを嫌う傾向があります。とくにメントール系のハッカやハーブ系のにおいには敏感です。市販のハッカスプレーや、専用のコウモリ忌避スプレーは、軒下や通気口など、出入りが疑われる場所に吹きかけるだけで簡単に対策できます。効果は時間とともに薄れるため、定期的な噴霧が重要です。
超音波撃退機
コウモリの聴覚は非常に発達しており、超音波で空間を把握しています。この性質を利用した超音波撃退機は、彼らにとって不快な音を発して寄せつけない環境を作ることができます。電池式やコンセント式の製品があり、屋外用の防水タイプも選べば幅広い場面で使えます。
センサーライト
光に敏感なコウモリに対しては、動きに反応して点灯するセンサーライトが効果的です。人感センサー付きのライトを軒下やベランダなどに設置することで、近づいた瞬間に強い光が当たるため、居心地の悪さを感じさせることができます。夜間に多く活動するコウモリの性質にマッチした対策です。
防虫ネットやパンチングメタル
物理的な侵入を防ぐには、通気口や隙間をふさぐことが重要です。防虫ネットやパンチングメタル(金属製の穴あき板)は、空気の流れを確保しつつコウモリの侵入を防げます。DIYで取り付けできるものも多く、コストを抑えながら対策を進められます。
フクロウなどの天敵の模型
コウモリはフクロウなどの大型の鳥を天敵として警戒しています。そのため、これらの模型を軒先やベランダに吊るしておくと、視覚的な威嚇効果が期待できます。ただし、時間が経つと慣れてしまう可能性があるため、設置場所や角度を定期的に変える工夫が必要です。
このように、コウモリ対策にはさまざまなアイテムが活用できます。それぞれの特性を理解し、複数を組み合わせて使うことで、より効果的な防除が実現できるでしょう。
コウモリを追い出す際の注意点

コウモリを家から追い出す際には、ただ外に出せばいいというわけではありません。不適切な方法やタイミングによって、逆に被害が拡大することもあるため、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
生き物としての扱いに配慮する
まず知っておきたいのは、コウモリは「鳥獣保護管理法」によって保護されている動物であるということです。勝手に捕獲したり殺処分したりすることは法律で禁止されています。そのため、「駆除」ではなく「追い出し」に徹することが基本となります。
繁殖期の作業は慎重に
特に注意したいのが、5月〜7月ごろの繁殖期です。この時期には親コウモリが子育てをしている可能性が高く、親だけを追い出してしまうと巣に残った子どもが餓死してしまうことがあります。これが死骸による悪臭や衛生被害の原因にもなりかねません。
出入り口を確認してから封鎖する
出入り口の封鎖は、すべてのコウモリが外に出たあとで行うようにしましょう。事前に天井裏や通気口を観察し、夕方の活動時間帯に確認することで、出入りルートを把握しやすくなります。封鎖の際には一方通行の出口を活用するのも効果的です。
閉じ込めないよう細心の注意を
間違ってコウモリを建物内に閉じ込めてしまうと、逃げ場を失った個体が室内に出てきてしまう恐れがあります。また、フンや尿による汚染、死骸による悪臭といった二次被害も発生しやすくなります。作業後は再度侵入がないか確認するようにしましょう。
追い出し後の再侵入を防ぐことも大切
追い出しが成功しても、元の環境がそのままでは再び戻ってくることがあります。小さな隙間を目張りしたり、忌避スプレーを使用するなど、再侵入を防ぐための対策も同時に進めていく必要があります。
このように、コウモリの追い出しには注意すべきポイントがいくつかあります。安全かつ確実な対策のためにも、作業に不安がある場合は専門業者に相談するのも一つの方法です。
コウモリ 嫌いな音を活用した対策まとめ
- コウモリはキィキィやチューチューという高音で鳴くことがある
- 夜間に聞こえる羽音や擦れる音もコウモリの存在を示す手がかり
- 高周波や超音波を不快と感じて逃げる傾向がある
- 強い光や音はコウモリにとって落ち着かない環境となる
- ハッカ油やナフタリンのような強いにおいも忌避効果がある
- YouTubeの忌避音動画を活用すれば手軽に対策ができる
- コウモリは音によるストレスで巣を離れることがある
- モスキート音は一部の個体に効果がある可能性がある
- 害獣対策アプリの超音波機能は一定の忌避効果が期待できる
- スマートフォンのスピーカー性能によって効果に差が出る
- アプリ使用時は人やペットへの影響に注意が必要
- 高音だけでなく動く物や光と併用することで効果が高まる
- コウモリは強い光を嫌い、活動が制限されることがある
- 色そのものよりも明暗の差や反射に反応しやすい傾向がある
- 音による対策は補助的手段として他の方法と組み合わせるのが効果的